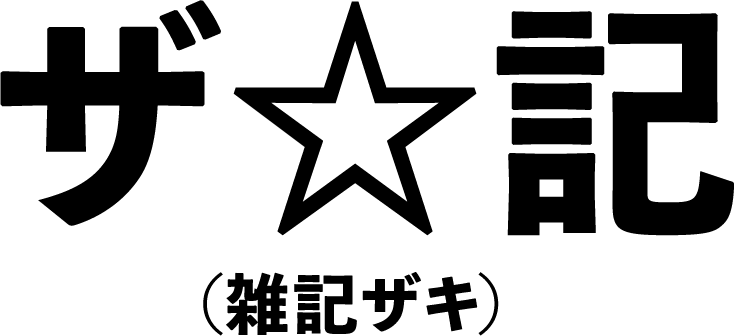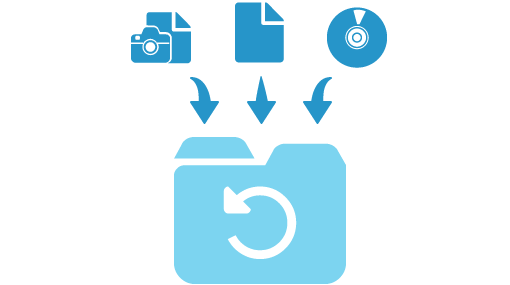文中に登場する、もしくは今後予定、そして自分が取り組む農法などの「用語」を書籍から引用しまとめています。
書籍の引用は iPhone APP「ClipOCR」を使用。誤認識については随時修正。
自然力を生かす 農家の技術 早わかり事典(農文協 編)
小力技術
「小力」という言葉を「現代農業」誌上で初めて使ったのは群馬県板倉町のキュウリ農家・松本勝一さんだ(九四年)。板倉町は、七〇年代に構造改善事業によるハウスキュウリの専作化を進め、キュウリの生産量日本一を誇ってきた。しかしその後、経営を引き継ぐ若手は少なく、農家の高齢化が進んでいる。
松本さんもかつては多収をねらって肥料や資材を多投し、がむしゃらに頑張っていたが、年齢や病気で体力が衰え、それまでのやり方を大きく変えるようになった。キュウリの株間は一mの超疎植にして、ピンチや誘引作業もせず、好き勝手な方向に枝を伸ばした。ベッドもわざわざ作り直すのをやめて、表層に発酵鶏糞を施すだけの春夏連続使用にした。
手間を減らすことが一番の目的であったが、キュウリをのびのびと育てたことで、キュウリの潜在力が発揮され、収量や品質はむしろ以前よりも上がった。
産地では標準的な栽培基準に添うことがふつうで、松本さんの用に身体の変化にあわせて栽培法を大きく変えてしまうという農家はあまりいなかった。松本さんはこのやり方を、単に作業手順を抜く「放任」とも機械や資材を導入して作業量を減らす「省力」とも意味が異なるとして、「小力栽培」と呼んだ。。小力という言葉には、「無理に作物をコントロールしようとせず、もともと作物がもっている力を引き出すようにしてやれば、結果として人はさらに小さい力ですむようになる」という意味が含まれている。
小力技術は、とくに高齢者や女性に支持された。高齢者や女性は、若者にくらべて力が弱くスピードも遅い。しかし、経験を生かした洞察力や、丁寧な作業を持続できるなど、「小さい力」を使いこなす点では優れている。
その後、さまざまな「小力技術」に目が向けられるようになった。イネのプール育苗では、水の保温力を活かすことによって、かん水や換気作業がラクになるだけでなく、病気が減って農薬散布も不要になった。合鴨水稲同時作では、除草剤を使わなくても草を抑えることができ、肥料もいらなくなる。さらに、質のよい肉が生産できる。果樹栽培では、雑草のナギナタガヤを生やすことで、中耕や除草作業が不要になり、自然に枯れてそのまま有機物の補給にもなる。バンカープランツは天敵のすみかを作ってやることで、天敵の力を引き出し、農薬散布を激減させることができる…。
小力技術とは、地域の風土や自分の田畑の土にあわせて、自然や作物の力を最大に引き出す、栽培技術の個性化であるともいえる。
「キュウリは秀品も多いし伸び伸び仕立てが一番、小力的である」編集部94年11月号
土ごと発酵
未熟な有機物を土の中に大量にすき込むと、土中で分解して有害なガスが発生することがある。また、材料にオガクズなどが多い場合は、窒素飢餓がおきる。このため従来は、あらかじめ有機物を発酵・分解させた完熟堆肥を投入するか、緑肥など生の有機物をすき込むときは種播きまで十分な期間をおくという方法がとられてきた。農家にとって土づくりはもっとも大切な仕事であるが、大きな手間と時間がかかる作業でもあった。
これに対し、一部の篤農家の間では、未熟な有機物を表層に 施用する方法も行なわれていた。未熟でも、地中深くに入れなければガス害などがおきず、有機物が微生物の栄養分になって土がよくなると言われてきた。それは、自然の土壌のように「土を上から耕す」と表現された。
九〇年代に、田植えあとの田んぼに米ぬかをまくと、雑草を抑える効果があることが報告され、全国各地の農家がこれを試みた。その過程で、土壌の表層で有機物が発酵・分解すると、抑草効果のみならずさまざまな現象がおきることがわかってきた。これは従来のわらマルチなどとは目的や様相が異なる。そこで「現代農業』誌では、この土壌の表層で有機物を発酵・分解させる方法を「土ごと発酵」と呼んだ。
畑の土の表層に米ぬかなどを投入すると、カビや細菌など好気的な微生物が繁殖しはじめる。微生物はさまざまな酵素や酸を分泌して、有機物を分解・吸収する。さらに、これらの有機酸は、鉱物化している土中のミネラルを溶出させ、微生物自身や作物がこれを吸収しやすくする。やがて、カビの菌糸や微生物が生成した粘り気のある代謝産物によって、土壌粒子同士が結合し、団粒構造が形成される。ミミズがふえてさらに団粒をつくる。
いっぽう、湛水した水田に米ぬかなどをまくと、嫌気性の乳酸菌や酪酸菌によって発酵がおきる。微生物は、有機物や周辺の土壌をこなごなに分解するが、水中のために微粒子同士の再結合がおきず、クリーム状のトロトロ層が形成される。トロトロ層の中は、有機酸によって水田土壌中の鉱物リン酸やミネラルなどが溶出しやすくなっている、さらに、雑草の種子がトロトロ層の中に埋没して発芽できなくなる。発芽しても、トロトロ層中の有機酸が雑草の根に害を与える。イトミミズがふえると、泥の攪拌効果によって雑草の抑制、ミネラルの溶出効果はさらに高まる。
土ごと発酵を成功させるポイントは、①有機物を深くすき込まず、表層の土と浅く混ぜるかマルチのように表面に置く。②畑で緑肥などを土ごと発酵させるときは、好気的な条件を保つために刈って少し乾燥させてから浅くすき込む③米ぬかや海のミネラルを混ぜると、発酵・分解がスムーズに進む。
土ごと発酵は、堆肥やボカシ肥をつくって外から持ちこむのではなく、作物残渣や緑肥などその場にあるものも利用できるのでラクで低コスト、小力の土つくり法なのである。
「土ごと発酵」で田畑に菌をとりこむ」8年10月号
雑草緑肥
畑の雑草をそのまま緑肥として利用すること。市販されている緑肥と違い、種代がかからず、種をまく手間も省けるので、近年は身近な雑草を緑肥として生かそうと考える農家がふえている。
愛知県豊橋市の水口文夫さんは、雑草が生えた夏の畑(豊橋あたりでは夏が端境期)に尿素をふったところ、草勢が旺盛になり、ほかの雑草を抑えてメヒシバ・イヌビエ(イネ科)が優占し、生育がそろった。穂が出るころ、ハンマーナイフモアをかけて細かく粉砕し、二~三日乾燥させてからすき込んだ。その結果、堆肥・ソルゴーをすき込んだ畑より、後作のカリフラワーの収量がよかった。排水性もよくなった。畑が空いている時期に、雑草をなくそうと耕うんして裸地にすると、地力が消耗して損失が多くなる。「夏の畑耕しや裸地は貧となる」という古老の言い伝えもあるという。
「稲作では稲刈りあとの田んぼに、スズメノテッポウ(イネ科)やカラスノエンドウ(マメ科)が自然にふえるが、これを緑肥としてわざとふやす農家もある。カンキツの草生栽培用の緑肥として脚光をあびているナギナタガヤも、もとは関東以西に勝手に自生していた帰化雑草である。
堆肥や肥料を入れて土づくりした農地が一番肥沃と考えている人が多いが、じっさいには、森林や草地のほうが、炭素・窒素の成分量が多い。植物が何十万年もかけて肥沃にした土地や、河川によってそこから流れ出た肥沃な土壌を生かして農業は営まれてきた。
「土はやせない、手間をかけない、カネもかけない」水口文夫98年7月号
竹肥料 (竹繊維)
竹を植繊機などの特殊な機械にかけ、繊維状に細かく粉砕したもので、ピートモスのようにフワフワしている。また竹をこなごなに粉砕した竹粉や、のこぎりくずも同様の効果
がある。
竹の大部分を構成しているのは、セルロース、ヘミセルロースなど繊維質(炭水化物)である。窒素、リン酸は少なく、灰分ではカリとケイ素が比較的多い(葉っぱには窒素が多い)。竹は暗渠の材料として利用されるように、もともと分解しにくい素材である。
C/N比が高く、竹繊維だけを土中に入れると、窒素飢餓をおこす。そこで、家畜糞尿などと組み合わせて堆肥化するか、硫安と一緒に施用して窒素飢餓を防ぐ。
竹繊維の性質を生かす利用法は、マルチとして使うことである。布団のように土の表面を覆うことで、水分や温度を安定させることがてきる。さらに、腐食化して排水性、保水性など土壌の物理性の改善にも効果がある。また竹を施用すると病害虫につよくなるといわれ、ケイ酸の働きによると考えられる。
「竹肥料マルチでおいしくなった、休まなくなった」編集部04年10月号
竹やぶで土着菌(ハンペン)
竹やぶで土着菌を採る茨城県の松沼憲治さん。種菌のつくり方は、土着菌(ハンペン)5つかみと、40℃くらいにさましたご飯を混ぜる。翌日これを15kgの米ぬかとあわせ、米ぬかの重さの3分の1の水を加え、コモをかけておく。発熱したら米ぬかと水を足して増量。10~15日して白い歯がまわったらできあがり。肥料袋やコンテナに入れておく。ボカシをつくるときに全体の重さの1割の種菌を混ぜる
「16ページキャプション」
木炭・竹炭
「地球温暖化が大きな環境問題となり、植物由来のエネルギー源である、炭の価値が近年見直されている。農業への炭の利用も、かなり広く行なわれるようになってきた。
炭は炭化温度によって保水性・四・CECの値などにかなり差があるが、農業利用には、五○○~六OOCの低温で焼いたものがむしろ望ましいとされる。農家が自分で農業用に焼く場合、もっとも簡便なのは伏せ焼きで、立て穴を掘り、せん定枝などをどんどんくべて、最後に土をかぶせ炭化する。
炭は表面積・空隙が多く、土に施すと地温を安定させたり、通気性、透水性、保水性を高める効果がある。また、炭に含まれる灰分には、カリ・リン酸・カルシウムなど、植物に必要なミネラルがバランスよく含まれている。そして、もっとも注目されているのは、炭が微生物をふやす働きである。松橋通生氏(元東海大学教授)によると、炭からでる音波をたよりに、好炭素菌(バチルス属が多い)が炭の周囲にあつまり、どんどん増殖するという。さらに、リン酸吸収を高めるVA菌根菌などがふえることも明らかになっている。
炭の力をうまく引き出すには、炭単独で使用するよりも、①ボカシ肥や堆肥にまぜる②アルカリ性なので木酢や過リン酸石灰と一緒に使う③リン酸が少ないのでリン酸肥料を一緒に施すとよい。
この他にも、家畜の下痢止めや糞尿の悪臭除去、水質浄化、農薬の吸着など、さまざまな炭の利用法がある。
「特集 もっと使えるぞ!炭」9年1月号/「竹炭・竹酢液のつくり方と使い方」岸本定吉監修 池嶋庸元著